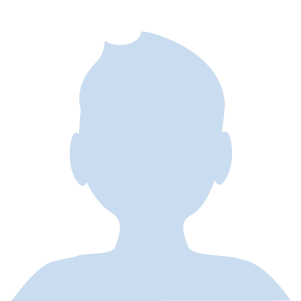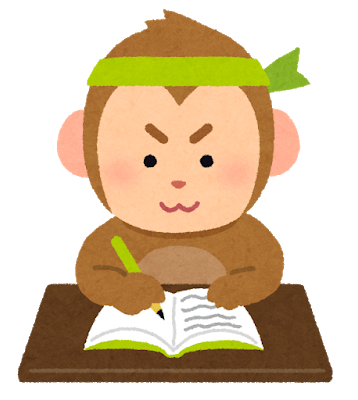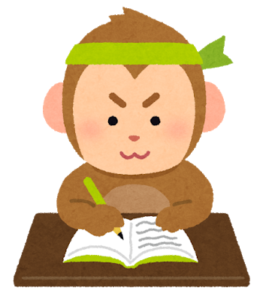こんばんわ。介護士のがんちゃんです。
今日は少し重いテーマである「看取り介護」の話をしたいと思います。
現在多くの施設で行われている看取り介護。看取り介護は在宅よりも施設の方が圧倒的に多いです。
その理由は
- 家族の負担
- 介護のプロにお任せをすることで安心・・・
ということが多いと思います。今回は実際の施設で行われている看取り介護を紹介します。
看取り介護とは?

看取り介護とは延命治療(点滴や酸素吸入)を行わず、自然な形で亡くなられるまでの間を介護することです。
と思われる方もいると思いますが、介護施設に入所されている方はほとんどが高齢者であり、延命治療を行うことで、かえって苦しんでしまったり、辛い思いをさせてしまう事もあります。
看取り介護っていつから行われるの?
それぞれの老人ホームによって判断基準は様々でありますが、私の働いている特別養護老人ホームでは経口摂取(食事を口から食べること)が難しくなってきた段階で、キーパーソン(身元引受人)と看取り介護の契約を行っています。
食事ができない状態というのは
- 食べる事でムセてしまう。そのことにより誤嚥性肺炎や窒息のリスクが極めて高い
- 食べる。という動作を忘れてしまい、口の中に食事や水分を入れても飲み込めない
- 食事介助を行っても口を全く開けない
という状態です。
これらの状態が数週間から数か月経過しても、変わらず食べられず回復の見込みがないと、医者の判断で看取り介護の対象となります。
老人ホームが看取り介護を開始するとき
老人ホームで看取り介護を開始するときは、医者、キーパーソン、施設相談員で今後の方向性を話し合います。
この日の数日から数週間前に施設からキーパーソンへ連絡が入り、家族の中でも今後の方向性を話し合って頂きます。
看取り対応を希望されない場合は
- 入院し治療を選ぶか
- 介護療養型医療施設を紹介
といった対応をするケースもあります。(介護施設では対応が困難の為)
看取り介護開始
看取り介護が開始されたからとすぐに亡くなるという訳ではありません。
人によって様々です。看取り契約後に「食事が食べられるようになった」という方も実際にいるため、一概にどのくらいとは言えません。
しかし、いつ急変してもおかしくないため面会に行けるときは短時間でも顔を見に行ってください。何よりも利用者様が喜びます。
看取り介護の食事

看取り介護の方のほとんどは経口摂取が難しい方々です。
しかし、その人たちには何も食べさせなくて良い。という考えはありません。家族の方から昔好きだった食べ物を聞いたり、口当たりの良いアイスやゼリーなどを提供し他の方より時間をかけて、少しでも食べて頂いています。
(少しとはスプーン1口、それが難しい人には口を湿らせる程度の量となります)
食事の負担も考える
私の介護施設でも毎回看取り介護の食事については議論になります。
「今までほとんど食べられていない方に急に一食分全量食べた」という事がありました。話を聞くと口を開けたから、食べてもらった。というものでした。
でも考えてみて下さい。その方たちは今まで食事を摂れずにいた人です。急に大量の食事すると
- 気持ち悪くなる
- 胃がびっくりする
- 下痢を起こす
ということが十分に考えられます。
食べられるからと一気に全量提供するのではなく、細目に少しずつ提供した方が身体への負担は少なくなると思います。
看取り介護のおむつ交換
基本的には他の利用者様と方法は同じですが、側臥位(横向き)にすることで、息切れを起こす方もいますので、職員2名でおむつ交換を手際よく行っています。
重要なのはおむつ交換のあとです。
おむつ交換後には体位交換を行います。その時にシーツや衣類にシワが出来ていると褥瘡(じょくそう)になる可能性も高いです。栄養も十分に摂れないためチョットしたことが余分な体力を消耗してしまいます。
体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまうことです。
特に寝たきり状態の高齢者に多くみられる症状です。
看取り介護その他の対応
バイタル測定
看取り介護では毎日バイタル測定を行います。血圧・脈・体温・酸素飽和度(血中の酸素の濃度を測ること)の測定し、変わりがないか、苦しそうではないかと言った観察を行います。
その内容を記録として残しているため、家族の方が見たいときには見られるようにしています。
家族が宿泊できるようにする
家族の方が泊まることも可能な施設もあります。最期を見届けたい方も多く、いつ訪れるかは分かりません。そのため家族が順番に泊まることもあります。その際は何か変わったことがあれば職員に報告し、対応してもらってください。
看取り介護は個室に移動することがほとんどですが
- 家族の写真や花を飾る
- 音楽が好きな人には音楽を流す、テレビをつける
- 大事にしていた物や洋服は個室に持っていく(飾る)
というような環境面での変化をなるべく少なくすることも大切です。
本当の最期を迎えるときには様々な兆候があります

最期を迎えるときは人それぞれ兆候が異なります。
- 体温が上昇する
- 手足が冷たくチアノーゼ(手先や足先の抹消から紫色になること)の出現
- 無呼吸状態(呼吸が止まり10秒から60秒後に呼吸を再開する)を繰り返す
- 努力呼吸になる(肩を上下させ呼吸をすること)
といった兆候が表れます。この兆候があっても個人差があるため絶対すぐに亡くなるということではありません。
しかし、本当に悲しく、寂しい事ですが、最期が近づいてきています。そのため、なるべく多くの声掛けをおこなったり、手や足を摩るといったことを行ってみてください。
反対にそれ以外の事は出来ないのが本音です。
また呼吸状態が悪くなると、見ている家族や職員も辛くなります。そのようなときこそ、声を掛けてあげてください。
看取った後にできること
これはひとつしかありません。
「ありがとう。お疲れさま」と伝えることです。
まだまだ頑張ってもらいたい気持ちは十分に分かりますが、高齢の方がほとんどであり、本当に頑張ったと思います。
もちろん家族と職員が一緒に涙することもあります。その涙はきっと利用者様には届いています。思う存分涙は流して良いと思います。
その後介護職員はおむつ交換や清拭を行うことは出来ますが、処置というものはできません。医者の死亡診断を受けてからでないとできないので注意してください。
看取り介護のわたしの実体験
実際介護施設で働いていると、この時を迎えることもあります。中には家族が遠方であったり、疎遠の方もいらっしゃり、最期を家族と迎えることが出来ない事もあります。
その時には私たち介護職員は家族のように関わりをもっています。
数年前の話ですが、90代後半の女性利用者様がいました。この方は身内がいないため最期を夜勤介護職員2名で看取りました。
その中にいた私は90年以上生きた方の最期を一緒に過ごすことができ、
「本当にありがとう。私を選んでくれてありがとう」
と心の中で言ったことを覚えています。
数年という短い間ではありましたが、この時たくさんの思い出が脳裏に浮かびました。
まとめ
現在約70%以上の介護施設で看取り介護を行っています。
私の意見ですが、家族の最期を介護施設にお願いすることは、家族にとっても、利用者様にとっても良い事だと思います。
ただ、多くの高齢者の希望は
「自宅で最期を迎えたい」
と考えています。少しでも自宅のような雰囲気でお見送りすることはとても大切という事を忘れてはいけないと思います。
今後看取り介護をお考えの方は、まずは看取り介護を行っているのかという事を介護施設に確認することをおすすめします。